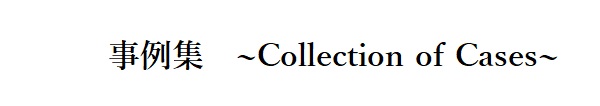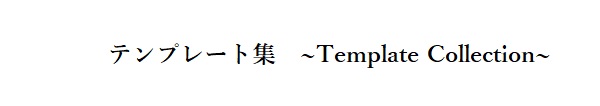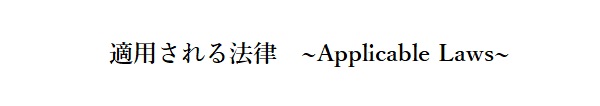実子誘拐(連れ去り)を許さない
PREVENTING PARENTAL CHILD ABDUCTION~
日本国内において、親権争いを優位に進めるため、実子誘拐による一方的な親子断絶行為が頻発し、実子誘拐を起因として、児童虐待による子どもの死や被害者親の自殺など、おぞましい事態が数多く発生している。
*令和3年の「子の引き渡し」申し立ての新規件数を1日平均で換算すると、1日に6~7件の申立てが行われていることになる。
これらを踏まえて国会や報道等では、実子誘拐は既に家庭の問題ではなく、社会問題としての認識が社会通念上一般的になってきている。
この実子誘拐において、もっとも重要で無条件で捉えなければならないことは、被害を受ける子ども達のことである。子どもにとって実子誘拐による親子断絶は、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では拉致誘拐や児童虐待として一般的に認知されている。
日本における実子誘拐被害者のコミュニティーとして本会を立ち上げると共に、その実情を世界に発信することを目的とする。
Tweets by jinkenheros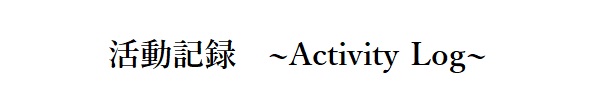
両親や祖父母から愛情と養育を受ける子どもの利益より、共産党系弁護士の利益を守る 神奈川県警人身安全対策課長 柳博泰 の共同親権法改正等の社会要請に逆らう差別対応への改善要請
令和7年11月25日全子人権ヒ第024号 警察庁統括審議官 土屋暁胤 殿<供 覧>衆議院内閣委員会委員長 山下貴司 殿参議院内閣委員会委員長 北村経夫 殿神奈川県議会防災警察常任委員会委 …
長野地検 鈴木忠彦 副検事の犯罪及びDVの助長、並びに共同親権改正法等の社会の要請に逆らい、子どもの利益を侵害する親子虐殺的な差別対応に対する改善要請
令和7年11月25日全子人権ヒ第022号 最高検察庁検事総長 畝本 直美 殿 <供 覧>衆議院法務委員会委員 小竹 凱 殿参議院法務委員会委員 嘉田 由紀子 殿法務大臣 …
埼玉県立○○○高校の教員による社会の要請に基づく犯罪行為及びDVとなる実子誘拐事件による親子断絶被害から子どもの利益を守るための要請
令和7年11月25日全子人権ロ第18号 埼玉県知事 大野 元裕 殿<供 覧>埼玉県議会議長 白土 幸仁 殿埼玉県教育長 日吉 亨 殿教育局教職員課長 …
子どもの連れ去りが“犯罪”とされる国際社会とそうではない日本
日本では、離婚前後に一方の親が子どもを無断で連れ去る「実子誘拐」が長年“民事トラブル”として扱われてきました。しかし国際的な視点に立つと、この扱いは大きく遅れていると指摘されています。欧米諸国では親 …
「子どもの関係性を奪うという暴力:離婚係争中の連れ去りと日本における人権意識の課題」
2025年6月9日 追記はじめに日本では、離婚の係争に伴う「子の連れ去り」や「実子誘拐」と呼ばれる現象が、長年にわたり放置されてきました。親権争いの一環として、片親が子を連れ去ることで、もう一方の親と …